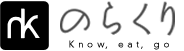佐渡島で漁師さんのお仕事を体験!
島の潮は生き物すべてをやさしく包み込む
いっちきました!ここは日本海沖、新潟県に属する沖縄本島に次ぐ広さの離島、「佐渡島」。
前回の記事では、佐渡島で柿農家さんでの援農体験ワーキングホリデーでしたが、今回は待望の水産業の体験レポが実現! 佐渡島のみんさん、多謝!
 農業と二分する日本の食をささえる漁業。最近は化石燃料の高騰などでその現状もマスコミを通じて世間に伝えられていましたが、実際、農業問題ばかりがマスコミに取りあげられているのが現状。農業と同じく漁業も、担い手問題や海外からの輸入食材に対する価格下落、食文化の変容など深刻な問題を抱えています。のらくり隊初の「漁業体験レポート」を佐渡島を舞台にお伝えします。
農業と二分する日本の食をささえる漁業。最近は化石燃料の高騰などでその現状もマスコミを通じて世間に伝えられていましたが、実際、農業問題ばかりがマスコミに取りあげられているのが現状。農業と同じく漁業も、担い手問題や海外からの輸入食材に対する価格下落、食文化の変容など深刻な問題を抱えています。のらくり隊初の「漁業体験レポート」を佐渡島を舞台にお伝えします。今回、お伺いしたのは、高校を出てから50年以上、佐渡島の漁師一筋の佐藤半四郎さん、70歳。実家が漁師をされ当時は、小さな船で漁をされていたそうですが、半四郎さんが本格的に稼業を継ぐようになり、序所に近代漁業にかえて今のように安定して水揚げができるようになったそうです。
 最近は消耗品のエンジンを積替えそれだけで約1,000万円!もするそうです。現在は、息子さんご夫婦が新潟本土から佐渡島へU-ターンし家業を一緒に手伝い家族4人で漁師を営んでいます。息子さんは新潟県で会社勤めをし、新潟本土出身の奥様と出会い今は3人のお子さんに恵まれながら、毎日、朝はやくから漁にお父さんと二人で出て行きます。
最近は消耗品のエンジンを積替えそれだけで約1,000万円!もするそうです。現在は、息子さんご夫婦が新潟本土から佐渡島へU-ターンし家業を一緒に手伝い家族4人で漁師を営んでいます。息子さんは新潟県で会社勤めをし、新潟本土出身の奥様と出会い今は3人のお子さんに恵まれながら、毎日、朝はやくから漁にお父さんと二人で出て行きます。潮や天候にもよりますが一日2回ほど海にでられるそうで、男達(2名)は基本、海で漁を担い、女達(2名)が陸で網の片付けからその日穫れた魚を午後に漁業組合に出荷するという作業分担を行っています。
朝は大体6時前に一回目の漁に男達は出かけ、女達は陸で積卸しの準備をします。大体8時前後頃に漁から戻ると、船の上で素早く採れた魚を木箱に種類、性別、大きさに仕分けます。その後に網を一度、陸に引き上げ網に残った魚や海藻、ゴミをとる作業を行います。これが結構、手先の器用さとスピードが求められます。
あやとりのごとく、手間ひまかかる作業

アラフォー隊長、あやとりや機械配線の絡み、紐などが絡んだ状況の復帰作業は性格的に苦手(汗)。さすがに商売道具を無下に扱えませんから、ここは慎重かつ得意の念で、こちら側の網がからまないことだけをひたすら祈り作業を続行。見た目は真剣ですが、心は邪心にして「大しけ状態」(恥)。いゃ、祈りは通ずるもんです。普段は1人で器用に引き上げているそうですが、今回は息子さんが一緒に手伝ってくれました。
しかし、大変な作業。なにせ鮮魚ですから素早く作業を行わないと物がいたみます。しかもそれなりに重労働(汗)。
網の方は一旦、陸に揚げてゴミ取りをすると、今度はそれを籠に仕舞う作業を2人で一緒に行います。横巾、おおよそ10m弱ほど、長さ数十mほどある網をひたすらねじりや絡みを取りながら籠にリズミカルにしまいます。一回の漁で2枚から3枚の網を利用するとのこ。陸でのアラファー隊長の指南役はお嫁さん先生が丁寧に指導を施してくれました。
こちらはリズムも悪ければ自分が網に絡まるなど、何ともよろしく哀愁状態...(涙)。
豊かな食彩アイランド-佐渡島

今朝一回目の水揚げは、この季節そろそろ終りを迎える鱈や、ズワイガニ、毛蟹、ヒラメ、サメ!マト(ウ)鯛などなど。他に見た事のない深海魚なども多数あり、ほんと、資源の豊な地である佐渡島を再認識。2回目の漁ではアンコウやエイなども穫れ、そこそこの漁獲の水揚げ。素人には大きい魚の方が「デカイ獲物だぜ!」と鼻息あらくなるのですが、漁師さんからするとデカ過ぎるのも消費者が扱いづらいため商品価値は低いとのこと。難しいんですね、これまた。
そして待望のお昼ご飯、やっぱりこれですよ、これ!まさに下心丸出し、遠慮も「しらぬ存ぜぬ」なのらくり隊長、出して頂いた朝穫りのズワイガニみそ汁にかぶりつき。これが何も出汁をいれずに海藻と蟹だけで出した味わいなんて。磯の香りがほんとう、山川豊ですぜ(笑)。そしてこの時期に穫れる真鱈のフライや、鱈の子、コレが直径が500mlのペットボトルくらいあるんです!まさに撲殺できる位の極太(痛)。
 それを昆布で巻いてるのでこれまた美味!お酒にもい合うでしょ。あっ、まだ後半戦のお仕事もあるのでしばし、妄想に止めます。
それを昆布で巻いてるのでこれまた美味!お酒にもい合うでしょ。あっ、まだ後半戦のお仕事もあるのでしばし、妄想に止めます。
そんなよそモンが食事をぱくついていると、お嫁さんは食事を手短にすませ、空いた時間で今度は夕食の仕込みなども手際良く行います。ほんと、みなさんの息があつたチームワークと手際の良さに感激&感動です。さすが、家族経営の絆、これぞファミリーの姿。
出荷作業はウォール街一流トレーダーのごとし

お昼休憩を挿んで、午後は女性陣に同行させてもらい佐渡島の水津(すいづ)にある漁業組合に魚の出荷に同行させてもらいました。午前中に穫れた魚を今度はどの市場に出荷するかを決め、箱詰めします。これまたかなりの手間のかかる作業!魚を一旦、車から積卸し、消毒水でちゃんと魚を洗い、それから市場ごとに箱詰め作業を行います。形や大きさや数を計算して箱に振り分けていきます。

事前に前日の水揚げ量や競り値を確認し、明日の天候などを総合的に考慮した上で、どのこ市場に卸すかを漁組合で決めて出荷作業を行います。これままさに株のトレーディングのような状況。同じ物をすこしでも高く売るために女衆は情報を巧みに集めて陸で魚をさばくのでありんした。
第一次産業における水産業の姿
農業と大きく異なる点は、作付け面積から年間の収穫高をある程度予測できる農業に対し、同じ自然相手でも海に毎日、ひたすら定置網を揚げてその日に穫れる物を出荷するという作業は養殖でない限り、漁獲量は自然に委ねることしかできません。もちろん、漁獲保証の保険などに加入はしているそうです。しかし、ある意味、一種のかけでもあります。また、味の落ちると言われる産卵後の魚などは、箱一杯で100円の価値しか無いなど、コレをかえって輸送費や箱詰め費などの諸経費を考えると漁師さんの赤字になります。魚でも雄や雌でも味が異なるなど全ては食べる側のエゴで市場価格は形成されます。その日に出荷されない鮮魚は、漁師さん宅の食卓に並びながらも、一部は処分せざるえません。
自然の中から生命を頂くということ

佐藤半四郎さんご夫妻に昔の佐渡島の海と何か変化はあるか訊ねると、今のところは昔と変わらず佐渡島の海は奇麗なままだそうです。ただ、お父さん曰く、年々、穫れる魚がこまく(小さく)なっているそうで。息子さんも出荷出来るぎりぎりの大きさのもの以外は網から外して海に戻していました。
単に何でも水揚げすれば良い訳でもなし、自然はみんなの共有財産、そして未来へ引き続く「いのち」の未来銀行。都市部の物さえ売れればそれで良しという刹那主義で貨幣経済至上主義がどこかおかしな地球にしてしまったのでしょう。自然から遠ざかった生活を送る者に、気づきをもらえる有益な時でした。
漁協の出荷手伝いから戻ってくると、もう16時過ぎ。まだ男衆は網の手入れ、お母さんは残った魚をさばいたり、作業の最中。
 お嫁さんと一足先に作業をあがらせてもらい宿泊施設まで車で送ったもらう車中、いろいろと話しをしながら漁師さんの手間のかかる作業をあらために実感できたと伝えると、
お嫁さんと一足先に作業をあがらせてもらい宿泊施設まで車で送ったもらう車中、いろいろと話しをしながら漁師さんの手間のかかる作業をあらために実感できたと伝えると、「確かに本土でOLをしていた時とくらべ、ほぼ休みも無く一年毎日、漁の仕事をしているとなかなか遠出とかできないけど、楽しくなければ続きませんよ。働いた分だけ結果もはっきりしているところは漁業を営んでいて面白くも良かったと思えます」
佐渡島の潮のような輝いた笑顔で元気にこたえてくれました。最高に気分の良いシーサドドライブ。第一次産業は大変、そんな思い込みは現場の人たちには大きさお世話。そこで生活してる人達には、それが現実で日常だから、よっぽど「リーマンショック」なんかが非現実。実態の無いところで巨額の札束がうごめいている事自体がよっぽど"非日常"な世界。
海みて山に木を植える
今回は直前まで佐渡島のみなさんに水産業のお手伝い先の調整をしてもらい、縁があり佐藤さん一家のお手伝いをさせてもらい、漁師の手間暇かかる作業の一部を拝見させてもらいました。
佐渡島では本マグロも穫れたり、イカや南蛮エビ、ブリ、牡蠣、海藻、また内陸は佐渡米、そば、柿、みそ作り、
 椎茸、など書いたらきりがないくらい食彩風景の多彩な土地。その中でも漁を続けて日本の食卓と食文化に喜びを提供し続けてくれる漁師さんに感謝です。
椎茸、など書いたらきりがないくらい食彩風景の多彩な土地。その中でも漁を続けて日本の食卓と食文化に喜びを提供し続けてくれる漁師さんに感謝です。最後に、佐渡島の人から、こんな話しを聴かせてもらいました。
昔、佐渡島でも魚が穫れない時期があり、村の漁師達が集まり話し合う中、無口だったある漁師さんが翌日、1人で山に向かい木を植え出したそうです。何故、漁師が木を植えるかと訊ねるとその漁師さんは、
「この海は山から流れ出した水で豊かな潮が作られてる。だから、山に木を戻すんだ」
私たちが今、気づかなければならない事、やらなければならない事、それはこの漁師さんの話しが教えてくれている気がします。